車椅子マラソン
車椅子マラソン
スポンサードリンク
車椅子マラソンの歴史

まだ日本の車椅子が木製で作られていた頃、中村博士がイギリスでルードイッヒ・グットマン博士の研修を受け、脊髄損傷者の近代的治療を始め、車椅子スポーツを車椅子障害者のリハビリテーションと社会に出るための方法としてその普及に努めたのが1960年。その後、大分県身体障害者体育大会、国際ストーク・マンデビル競技大会、第2回国際身体障害者スポーツ大会などに出場。アメリカにおいては1974年に世界初の車椅子マラソンが開催されました。日本においても車椅子マラソンが徐々に浸透していき、1977年にはホノルルマラソンに日本選手が出場を果たしました。第7回のパラリンピックでは車椅子マラソンの部が加えられました。
車椅子ランナーの情熱
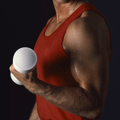
レーサーと呼ばれる軽量化された車椅子マラソン用の車椅子に乗って駆け抜ける選手たち。その速さは42.195キロを1時間20分台で走る選手もいます。大会においては障害の重度によってクラス分けがなされます。どんな障害者でも公平にレースに参加するためです。選手はその苛酷なレースを完走するため、体調はもちろんのこと、食事にも気を使い、体力づくりをしていきます。1981年にスタートした大分国際車椅子マラソン大会は平成18年には26回を迎え、25回大会では19ヵ国、320名の車椅子ランナーが参加しました。車椅子マラソンという苛酷なスポーツに情熱を傾ける障害者が増え、その姿は見ている者にも感動を与えています。
盲人マラソン

どんな障害者にとっても走る可能性はあります。車椅子マラソンだけでなく、視覚障害者のマラソンもあります。盲人マラソンには伴走者と呼ばれるガイドランナーが必要です。この伴走者の役割はとても大きいものです。伴走者と視覚障害者ランナーは紐を持って一緒に走るのですが、呼吸、リズム、速度など2人の息が合わないと記録にも響いてきます。また、視覚障害者ランナーが安心して、快適に走れるかどうかが伴走者の力にかかってきます。
健常者と障害者が一緒になって走り抜く盲人マラソン。お互いがお互いを理解することは簡単なことではありません。しかしその分、やり遂げた時の両者の充実感は図り知れません。日本盲人マラソン協会では、視覚障害者マラソンに重要な役割を担う伴走者の育成に力をいれています。
スポンサードリンク